大人のASDあるある~職場での“困りごと”と対処法~対人関係編
「他人の感情がわからない」「あいまいな指示がわからない」…もしかしたら、それはASDの特性かもしれません。今回のコラムでは、大人のASDの特徴や職場で起きがちな“あるある”の対人関係編を紹介し、対処法についても考えていきます。
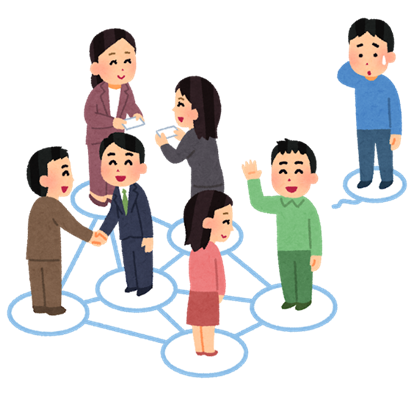
-目次-
1.ASD(自閉スペクトラム症)とは
2.大人のASDn特徴
3.職場での”ASDあるある”と対処法(対人関係編)
4.おわりに1.ASD(自閉スペクトラム症とは)
ASD(自閉症スペクトラム症)とは、生まれつき「人との関わり方」や「感覚の受け取り方」、「ものごとのこだわり方」に特徴がある状態のことをいい、主に以下の特性があると言われています。
①人との関わりやコミュニケーションが苦手
相手の気持ちや場の空気を読み取ったり、言葉の裏を読み取ること、自分の気持ちを適切に伝えることが難しいです。
②好きなことへのこだわりが強い
興味のあることに強く集中する一方で、関心の幅が狭かったり、いつもと違うやり方にストレスを感じやすいことがあります。
この他にも、人によっては以下のような特徴をもつことがあります。
・音や光、においなどに敏感すぎたり、逆に鈍く感じたりする
・手先が不器用だったり、動きがぎこちない
・睡眠がうまくとれない
・一つのことに集中しすぎてしまう(過集中)
・覚えたことをよく記憶している(記憶力が高い)
こうした特性は、見た目では分かりにくいため、周囲に誤解されることもあります。
2.大人のASDの特徴
子どもの頃は気づかれなかったが、大人になってから対人関係や仕事での困りごとを通じて気づくケースもあります。
例えば・・・
・自分の興味のある話を一方的に話し続ける
・場の空気や人の感情を読み取りにくい
・曖昧な指示や遠まわしな表現が分かりにくい
・一度決めた手順を変えることが苦手
・規則やルールにこだわる
こうした特徴から「融通がきかない」と思われることもありますが、興味のある分野には深い集中力と知識を発揮できるという強みもあります。
3.職場での“ASDあるある” と対処法(対人関係編)
①「時間あるときにやっておいて」が分からず混乱
ASDの人は曖昧な言葉や感覚的な表現を理解するのが苦手です。「テキトーに」「様子を見て」など明確な基準がない言葉や、「時間あるときにやっておいて」といった抽象的な言葉は、判断に困り、強い不安や混乱を感じることがあります。理解しづらく、「時間がないからしなくていい」などと受け止めることで、誤解が生じてしまいます。
↓対処法
指示内容で不明な点があれば、「その仕事は期限がありますか?」「いつまでに、どのくらいやればいいですか?」など5W1Hで具体的に確認するようにします。ほかにも、「だいたい」「なるべく」などの曖昧な指示を受けたときも、具体的な質問を返しましょう。
②言葉を文字通りに受け取る
「顔が広い」→「顔のサイズが大きい」のように比喩や慣用句をそのままの意味で受けとってしまい、意図と異なる理解をしてしまうことがあります。
↓対処法
分からないときは「今のってどういう意味ですか?」と確認する癖をつけましょう。また、本やアプリで、よく使われる慣用句を少しずつ覚える、日常会話で変なイメージになったら「たとえ話かも?」と意識しましょう。
③ASDの人は相手の表情や声のトーンなど、非言語的な情報を読み取ることが苦手です。例えば、「明日は雪でも降るんじゃない?」と笑いながら言われると、天気予報を確認し始める、など冗談や皮肉を本気の発言として受け取ってしまい、場の雰囲気から浮いてしまうことがあります。
↓対処法
冗談と本気を判断できないときは「これは本当の話ですか?」と直接確認してみましょう。また、相手の顔を見て、笑いながら言っていたり周囲が笑っている場合は冗談、真顔なら本気のことが多いので目安にしてみてください。
④思ったままを口に出す
見たことや感じたことをそのまま言ってしまい、「それは間違ってますよね」など断定的な言い方で相手を不快にさせてしまうことがあります。
↓対処法
たとえ正しい意見でも、感情のままに話すのではなく、まず「確かに」「そうですね」と共感を示し、意見が異なる場合は理由を添えて伝えましょう。話す前に少し考える時間を持つことで失言を防ぎやすくなります。
⑤目を合わせないと“冷たい人”と思われがち…
目を合わせずに話すことで「冷たい人」「そっけない」と思われてしまうことがあります。しかし、これは必ずしも無関心だからではありません。発達特性や緊張のしやすさなど、さまざまな理由で視線を合わせることが難しい方もいます。
↓対処法
相手の話を聞くときは手を止めて、目を見ることが難しければ目の下や眉間、口元に視線を向けるなど、関心を示す姿勢を意識しましょう。視線を直接合わせなくても、相手は“自分の話を聞いてくれている”と感じやすいです。

⑥雑談になると何を話せばいいか分からない
ASDの人は、会話の間の取り方や、何を話せばよいかを読み取ることが
苦手な場面があります。特に、目的のない雑談では「何のために話している
のか分からない」と感じ、距離を置いてしまいがちです。
↓対処法
無理に話の中心にならなくても大丈夫です。相槌や「そうなんですね」
「おもしろいですね」といった定型フレーズを用意しておくと安心です。
雑談中は聞き役に徹し、会話の終わりに一言コメントを加えるだけでも
印象は変わります。
ASDの特性による「あるある」は、一人で抱えるとしんどく感じることもあります。でも、練習や工夫を重ねることで少しずつ楽になったり、「こうすればうまくいく」という自分のパターンが見えてきたりします。当事業所では、相手の気持ちや場の空気を理解する練習としてSCIT(社会認知・対人関係トレーニング)に取り組んでいます。また、他にもSST(社会生活技能訓練)など、実際の場面を想定して練習できる方法もあります。
ひとりで頑張るのではなく、支援者や仲間と一緒に工夫していくことが、安心につながる大切なステップです。
4.おわりに
ASDの特性は、表情の読み取りや雑談の難しさなど、対人場面で誤解を招くことが少なくありません。「冷たい人」「空気が読めない人」と言われてしまうのも、理由が分からなければ大きなストレスになります。でも、それは“性格の問題”ではなく、“感じ方や伝え方の違い”です。対人関係も、自分の特性を知り、少しの工夫でうまくいくことがたくさんあります。苦手を否定するのではなく、「自分の取扱説明書」を相手にも少しずつ伝えていく。それが、無理なく人と関わっていくための大切な一歩です。
本コラムの作成にあたり、厚生労働省 社会・援護局「発達障害の理解~メンタルヘルスに配慮すべき人への支援~」(令和元年10月9日)および「大人の発達障害 仕事・生活の困ったによりそう本」(太田晴久監修)を参照しました。














