【うつ】うつ(適応障害) の仕事あるある
著者 臨床心理士/公認心理師・平野秀幸
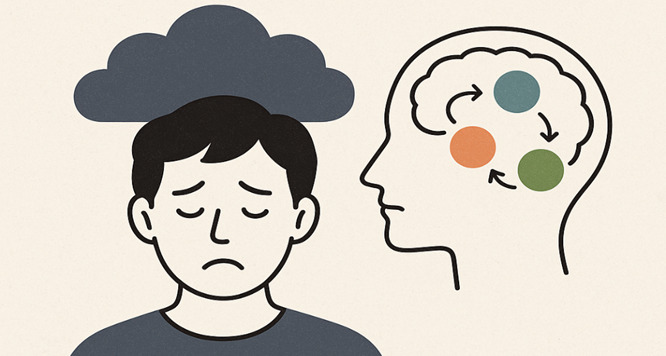
日々の仕事に追われている中で、皆さんの心や体は疲れていませんか?令和5年度の労働安全衛生調査によると、仕事や職業生活に関することで、強い不安、悩み、ストレスとなっている事柄があると感じている労働者は82.7%に上るそうです。このようなストレスは知らず知らずのうちにメンタルヘルス不調を招きます。メンタル不調を示すサインの中には、普段の職業生活の中で特に気にも留めず見落としてしまうものも多くあります。本コラムではそれらの見落としてしまいやすい不調のサインを、うつ(適応障害)の仕事に関する「あるある」としてご紹介します。
目次
●うつ病とは?
●うつ病の原因と症状
●うつ病の「仕事あるある」
●うつ病の「仕事あるある」にはどう対処する?
●まとめ●うつ病とは?
うつ病はテレビやインターネットなど様々なメディアで扱われることも多く、日々の生活の中のどこかで聞いたことのある病気かと思います。昔は「うつは病気ではなく、本人のやる気に左右されるようなものである」というイメージも多く聞かれました。しかし厚生労働省が示している「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」(以下、こころの耳)では、うつ病について以下のように説明されています。
「うつ病は、一言で説明するのはたいへん難しい病気ですが、脳のエネルギーが欠乏した状態です。それによって憂うつな気分やさまざまな意欲(食欲、睡眠欲、性欲など)の低下といった心理的症状が続くだけでなく、さまざまな身体的な自覚症状を伴うことも珍しくありません。つまり、エネルギーの欠乏により、脳というシステム全体のトラブルが生じてしまっている状態と考えることができます。」
精神医学では、うつ病は脳内の神経伝達物質の異常によるものであるとされています。そのため、本人の気の持ちようで何とかできるものではなく、医療による治療が必要な病気であると言えます。
●うつ病の原因と症状
うつ病は何が原因となって生じるのでしょうか?厚生労働省の「こころの耳」では、「うつ病を引き起こす原因はひとつではない」とされています。1つの原因だけでなく複数の要因が絡まりあって、うつ病は発症するとされています。例えば災害などの環境面での要因もあれば、人間関係のトラブル、家庭内のトラブル、職場や家庭での役割の変化(昇格、降格、結婚、妊娠など)も要因として数えられます。がんや糖尿病といった身体疾患もうつ病の原因として挙げられます。また完璧にしなければいけない、失敗してはいけないといった個人の考え方の傾向もうつ病の背景にあると考えられています。このことから、うつ病の原因は多岐にわたるとされています。
また代表的な症状については、気分の落ち込みや意欲、思考力の低下といった精神面での症状と、睡眠リズムの乱れや食欲不振や過食、頭痛や胃腸の不調といった身体面での症状の2種類があります。
●うつ病の「仕事あるある」
仕事をしている時間は私たちの1日の中でも、大きな部分を占める時間です。仕事の中では、うつ病特有の症状や変化が表れやすいと言えます。本コラムでは、仕事の中で見られやすいうつ病の症状や心身の変化を「あるある」としてご紹介したいと思います。
①遅刻や早退、欠勤が増える
うつ病は生活リズムにも影響を与えるため、睡眠の乱れにより朝に起きることが難しくなり遅刻が増えてしまうことがあります。また生活リズムの乱れから、風邪などその他の体調不良を招きやすくなり、早退や欠勤が増えることもあります。
②業務上でのケアレスミスが増える
うつ病を発症すると、注意力や記憶力、問題解決力などの認知機能が低下するとされています。例えば書類仕事をしていると誤字脱字が増えてしまう、簡単な計算ができなくなる、といった仕事のミスを防ぐために必要な認知機能に支障が出ることがあります。
③簡単なことでも決められない、仕事に何倍もの時間を要する
仕事に必要な判断力も同様に、うつ病の影響を大きく受けます。ひとつひとつの判断に大きく時間がとられるため、いつもなら短時間でできている仕事に何倍もの時間を要してしまう、簡単なことであってもすぐに選ぶことができなくなる、といった変化が生じることがあります。
④周囲との会話や口数が減る、表情が暗くなりひとりでいることが増える
うつ病になると悲しく憂うつな気分が続き、これまで好きだったことに関心も持てず、何をしても楽しくないという気分や意欲に関する症状が見られます。その影響から、職場の中で上司や同僚とのコミュニケーションの量が減少するとされています。憂うつな気分になることから、表情や顔色に変化が出ることが多いです。また人とのコミュニケーションを避けようとするため、休憩時間などにひとりで過ごす時間が長くなります。
●うつ病の「仕事あるある」にはどう対処する?
上記で示した「仕事あるある」はうつ病の発症に関する重要なサインとなると考えられます。このようなサインが見られた際には、産業保健スタッフや人事、医療機関などに相談するとともに、自分自身でできるセルフケアに取り組むことも大切です。例えば、睡眠や食生活の記録を自分でつけることで、自分で生活リズムの乱れに気づくことができれば、それが不調の改善への初めの一歩となります。また、仕事にメリハリをつけてうまく休憩をとれるようになることも、仕事のミス防止や効率をあげるために効果があると考えられます。周囲とのコミュニケーションの減少については、その人の考え方の傾向が関係している可能性もあります。うつ病の人には「きちんとしなければ」という完璧主義や、「自分が悪いからだ」という自責思考が、考え方の癖として見られることがあります。自分を苦しめてしまう考え方の癖に対しては、認知行動療法という心理療法が有効とされています。詳しくはワンモアのこちらのコラムをご覧ください。
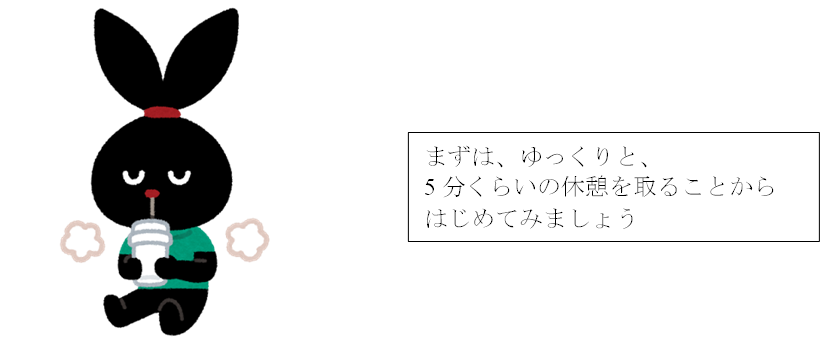
●まとめ
うつ病は15人に1人がかかる病気であるとされており、令和5年度の労働安全衛生調査では63.8%の企業がメンタルヘルス不調への対策に取り組んでいると回答しています。このことから、企業のうつ病に対する理解は今後ますます進んでくると思われます。しかしうつ病は個人によって病状の程度が異なり、すべての人が共通して同じ症状を有するとは限りません。自分自身にうつ病の影響でどのような症状が表れており、何に困難を抱えているかを自己理解できていることが大切と言えます。
ワンモアでは、認知行動療法などのプログラムを通してメンタルヘルスに関する知識を学び、ストレスや不調への対処法を身に着けることができます。また実際の仕事場面を再現して自身にどのようなうつ病のサインが出ていたのかを体験的に気づく機会も設けています。ワンモアの支援については、こちらをご覧ください。
プログラム – 就労移行支援と企業向けメンタルヘルスサービスを提供しています – ワンモア
○このコラムを作成するにあたって「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトこころの耳」 (https://kokoro.mhlw.go.jp/)を参考にしています。














