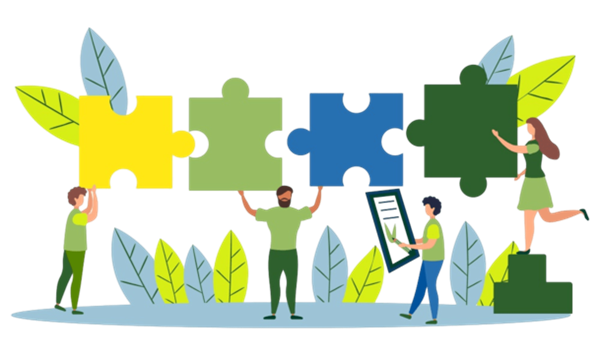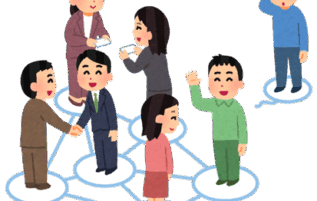高次脳機能障害のお仕事あるある
今回は、高次脳機能障害のお仕事に関する「あるある」をご紹介します。
目次
● 高次脳機能障害とは
● 高次脳機能障害の症状
● 仕事に関するあるある
● 周囲の理解が得られにくいという壁高次脳機能障害とは
事故や病気で脳に損傷を受けたことにより、注意・記憶・遂行機能などがうまく機能しないがゆえに、社会的行動が適切に行えず、日常生活または社会生活に制約がある状態のことを指します。見た目では分かりにくいため、周囲から理解されにくく、本人も「うまくいかない理由」が分からずに悩むことがあります。
高次脳機能障害は、脳外傷(交通事故・転倒など)や脳卒中(脳出血や脳梗塞)、脳炎、低酸素脳症などの後遺症として起こります。障害の程度や現れ方は人によってさまざまで、「日常生活はある程度できるけれど、仕事になると支障が出る」というケースも多く見られます。
(参照:国立障害者リハビリテーションセンター 高次脳機能障害情報・支援センター 高次脳機能障害を理解する)
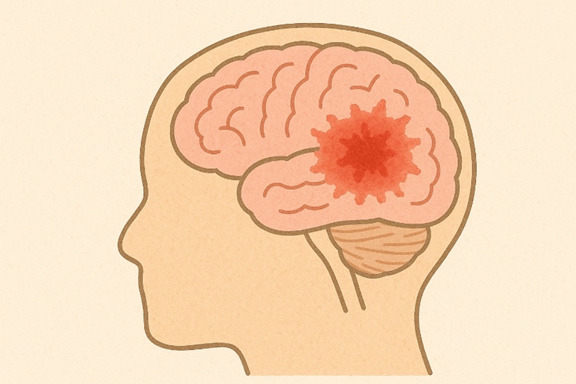
高次脳機能障害のコラムはこちら
「高次脳機能障害はわかりにくい?」 – 就労移行支援と企業向けメンタルヘルスサービスを提供しています – ワンモア
高次脳機能障害の症状
高次脳機能障害の症状として、主に①注意障害、②記憶障害、③遂行機能障害、④社会的行動障害が挙げられます。
①注意障害
・長時間集中し続けるのが困難
・周囲の音や動きにすぐ反応してしまう
・ケアレスミスが多い
・二つ以上のことを同時に行うと混乱してしまう
②記憶障害
・新しいことが覚えられない
・同じことを何度も質問する
・予定を忘れてしまう
・昔の記憶は比較的保たれていることが多い
③遂行機能障害
・優先順位をつけるのが難しい
・物事を計画立てて取り組めない
・一つのことにこだわってしまい、切り替えができない
④社会的行動障害
・場の空気が読みにくい
・相手の気持ちを想像するのが難しい
・我慢が効きづらくなる
・感情の起伏が激しくなる
仕事に関するあるある
◎集中力が続かない、やる気が出ない
例)周囲の音に気を取られて、ミスが増えてしまう

前頭葉や頭頂葉が損傷していると、注意の調整が難しくなります。そのため、周囲の刺激を受けやすくなり、注意が逸れ、どこまでやっていたか分からなくなったり、別のことに気がとられてしまったりすることでケアレスミスなどが増えることがあります。
自分で出来る対処法
・時間を意識する
例)作業時間を短く区切る(アラーム等設定)
・時間帯を意識する→集中しやすい時間帯を見つけて、朝一や体力がある時に難しい作業を行う
周囲が出来るサポート
・集中できる環境を整える
例)パーテーションで区切る、壁側に向かって作業する、静かな環境を選ぶ
◎指示の理解や記憶が難しい
例)指示を受けても途中で内容を忘れてしまい、間違った行動をとる

前頭葉や側頭葉の損傷によって、理解が難しくなったり、新しいことを覚えられなかったり、覚えているけど思い出せないということが起こります。また、メモをとっても、どこにメモをしたのか忘れてしまう…なんてこともあります。
自分で出来る対処法
・メモをとる時は同じノート/指定の場所に書く
・チェックリストの活用
周囲が出来るサポート
・口頭の指示だけではなく、視覚的な指示(文章や写真、見本など)も併せて行う
・一度に伝える情報は少なめにする(具体的に・簡潔に)
◎段取り・計画を立てることが苦手
例)何から手をつけていいのか分からず、作業が進まない
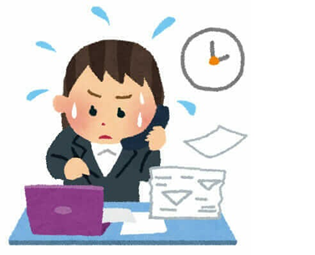
前頭葉や頭頂葉の損傷によって、順序立てて物事に取り組むことが難しくなることがあります。予測をしたりすることも苦手になりやすいため、想定外のことが起こった時に戸惑ってしまうケースもあります。
自分で出来る対処法
・優先順位を職場の方に教えてもらう
・想定外のことが起こった時の対処法を事前に決めておく
例)上司のAさんに伝える、深呼吸をする
周囲が出来るサポート
・作業の手順を見える化する(マニュアルやホワイトボードに貼る)
・業務をルーティーン化する→毎日同じリズムにすると、この時間はこの作業をすると覚えやすくなる
◎周囲とトラブルに発展しやすい
例)その場にそぐわない発言や態度をとる

脳の前頭葉などの損傷により、状況判断(場の空気を読む)・感情の抑制・他者の気持ちを想像する力がうまく機能しないため、トラブルなどが起きやすいことがあります。本人は悪気がなくやってしまうのが特徴で、本人もあとから後悔して落ち込むこともあります。
自分で出来る対処法
・事前にどんな場面が苦手なのかを知っておく
例)疲れている時、想定外のことが起こった時、注意された時など
・感情のチェックリストをつかう
・その場から一時的に距離を置く、休む
周囲が出来るサポート
・事前に共有されているサインが見られたら、声をかけて落ち着ける場所に案内する
・なぜそういった出来事が起こったのか一緒に振り返る
周囲の理解が得られにくいという壁
高次脳機能障害の大きな特徴は、「外見では分かりにくい」ことです。見た目は健康そうに見えるため、同僚や上司から「やる気がない」「だらしない」「適当な人」と誤解されやすく、孤立することもあります。また、本人自身も「なぜうまくいかないのか」が分からず、自己否定に陥ることも少なくありません。
高次脳機能障害は「見えない障害」であり、仕事の場面ではさまざまな困りごとが現れます。ただし、それは「能力がない」ということではなく、「脳の機能にサポートが必要な部分がある」ということです。同じ高次脳機能障害であっても、症状には個人差があります。まずはどんな症状があるのか、どういう時に困りやすいのかを理解して、周囲にも共有しておくといいでしょう。
本人に合ったペースと環境、そして周囲の理解があれば、自信を取り戻し、社会の中で活躍することも十分に可能です。重要なのは、「できないこと」ではなく「どうすればできるようになるか」に目を向けることです。
ワンモアでは、得意なことは伸ばしつつ、苦手なことに対してもどうすれば取り組みやすいのか一緒に作業を介して考えるプログラムや面談などを実施しております。
ご興味がある方は、随時見学や体験など行っておりますのでお問い合わせください!
就労移行支援と企業向けメンタルヘルスサービスを提供しています|ワンモア